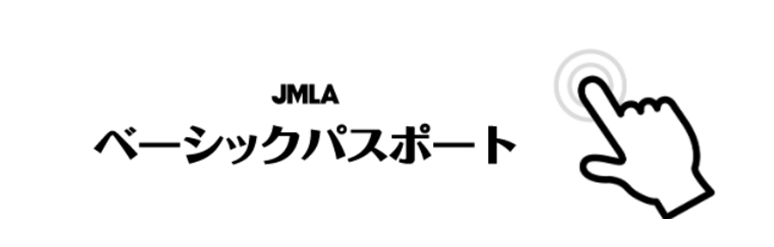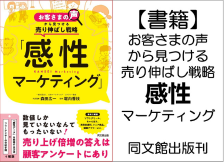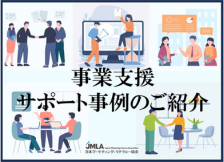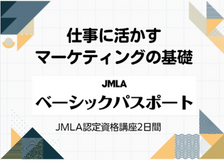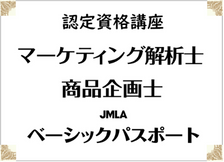「プロモーション」から「コミュニケーション」へ B2B2Cの失敗事例から学ぶ ヒト対ヒト
Facebook社が、社名をMetaに変えました。仮想現実空間「メタバース」を企業のメインドメイン(中心的事業領域)とするということだそうです。
メタバースとは、インターネット上に構築された、三次元仮想空間のこと。VRやARなどの技術を用いることで、仮想空間を現実世界にいるような感覚で体験することができます。
メタバースは、ユーザーとユーザー、ユーザーと企業を結ぶ新たな概念と言っていいでしょう。ゲームやソーシャルVRの他、バーチャルオフィスなどもメタバースの一つです。最近では、教育の現場や、美術館、博物館でも利用されているケースがあります。
メタバースは、あらたなコミュニケーションの舞台として機能し始めているのです。
メタバースそのものには、現在賛否両論あるようですが、ここではそのメタバースそのものではなく、マーケティングにおけるコミュニケーションの重要性に関してお話ししたいと思います。
マーケティング「4P」の意味的変化
マーケティングの戦略立案に必須の4Pという言葉がありますが、その4つのPのひとつに「Promotion(プロモーション)があります。
※「マーケティングの4Pとは」についてはこちらをご覧ください。
昔は言葉通りに、企業が商品やサービスをプロモート(Promote)する活動が「Promotion(プロモーション)」の主体でした。商品やサービスの特徴を宣伝することが重要だったのですが、その「Promotion(プロモーション)」の意味合いが近年変化してきています。
何故でしょうか?
それは消費者・顧客の情報収集能力が飛躍的に高くなったからです。
一昔前は、消費者・顧客は商品情報をテレビCMや新聞、雑誌などの企業広告活動から、情報を収集するしか方法がありませんでした。しかし現在は違います。
SNS等から様々な情報の入手が簡単にできるようになりました。個人でも情報収集が可能です。
様々なメディアが競って情報を発信しています。情報収集先を一つに絞らなくてもよくなりました。
SNS等で人々は情報を交換できます。企業本位ではなく、ユーザーの視点からも情報が得られるようになっています。
企業からの宣伝広告により商品の存在を認知したとしても、すぐには飛びつかず、周囲の信頼する人の評価など、レビューを参考にし、その良しあしを判断するようになりました。
「Promotion(プロモーション)」は「コミュニケーション」へ変化したのです。

メタバースは受け入れられるのか!?
「相棒」というテレビ番組(刑事ドラマ:season20 第13話「メタバース殺人事件」)でも、仮想現実空間「メタバース」を題材にした物語が繰り広げられましたが、いよいよ一般社会にもその時代が来るのでしょう。
コロナ過でリモートによる企業活動や教育活動が展開され、人々もその方法に慣れてきています。これは、メタバースの利用が多くなってきているとも言えることです。
しかし、実際に経験すると、「Web会議では人の感情が捉えにくい」という声や、「学生からは仲間と会えず、友達ができない」などという悩みも多く聞かれます。
これらの問題の本質は何でしょう?
それはまさしくコミュニケーションなのです。人は人とのつながりを求めます。
悲惨な例としては、電車内での凶行を起こした「小田急線 無差別刺傷事件」の犯人の理由も、「仕事に失敗し周りの人とうまく付き合えなくなった」という人とのつながりが問題だったようです。極端な例を挙げてしまいましたが、それくらい人は「人とのコミュニケーションが生きていくうえでとても重要」だということです。

人間の基本的欲求としてコミュニケーションは存在します。
つまり、企業がそのコミュニケーションに対応することは非常に重要であり、必然であると言えます。
コミュニケーションの方法は、テクノロジーの進化に伴い、発達した様々なツールやソリューションを利用するものに変化しました。
一般消費者が容易に情報を入手したり、自分自身で発信できるようになったわけですから、企業側にもますます対話力が求められるようになっています。
「メタバース」世界でも、企業は、消費者・顧客とコミュニケーションを取りながら、「人が何を欲しているのか?」を感じ、その要求にどのように応じるか、といった、「対話すること」が求められるのではないでしょうか。
プロモーションからコミュニケーションへ BtoBtoCの失敗事例から学ぶ
ここで一つ具体的に、B to B to C のコミュニケーション失敗事例を挙げます。
マンションの「管理会社(サービス提供会社)」と「管理組合(住民の組合)」と「個人としての組合員=住民・理事長」との間で起きたコミュニケーションの失敗例です。
マンションの管理会社は、契約しているマンション(マンションの管理組合)に対して月次の理事会運営を中心に、さまざまなサポートを提供しています。これまでは人的対応が中心でしたが、近年、ICT化(情報通信技術「Information and Communication Technology」)を進めており、その一つに決済があります。
これまでは、担当の営業が支払い用紙を準備して、マンションの管理組合の理事長に捺印をもらうために家庭訪問をして、決済を進めていました。
それをオンライン決済(ネットバンキング)に切り替えています。決済の都度、理事長宅に訪問しなければならなかったのが、管理会社の経理システムから自動送信するだけで済むので、何軒ものマンションを担当している営業担当者の業務負担が減り、効率化を図ることができます。
しかし、それまでの決済には、人と人のコミュニケーションがありました。住民が参加する理事会で決済承認をして、加えて決済金額と内容について、担当営業から説明をし、そこで初めて、組合の住民を代表する理事長が決済手続きを行っていたのです。
このフローがあったからこそ、安心して決済業務を管理会社に任せることができていました。しかし、フローがオンライン決済に切り替わった途端、理事会での決済承認もなくなり、何の決済なのか担当営業からの説明もなく、自動配信のみで決済を済ます流れに変わってしまったのです。
当然、説明もなく決済が行われてしまったために、住民たちがから不満が出てしまいました。
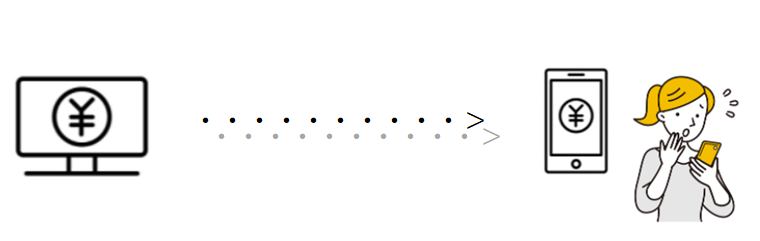
「決済および金銭のやりとり」は、「人と人のコミュニケーションが信頼を築き、その信頼の上に成り立っている」ことに、改めて気づかされたケースです。
このコミュニケーションの失敗は、住民代表の理事長からの要求で、決済承認を自動配信する前に、下記のステップを踏むことで解決しました。
Step1 理事会で決済承認を行う
Step2 オンライン決済の承認を行う人(組合の理事長)に対して、担当営業から電話などで、自動配信により決済承認を依頼する旨の連絡を入れる
決済の前に、人と人のコミュニケーションが事前に行われることで、管理会社の信頼が回復しました。
消費者・顧客が支払う対価とは、企業が提供する商品やサービスの価値に対する支払いです。
企業は、消費者が何を欲しているのか、そして自社の商品やサービスが、どのようにその欲求を満たすのかを真摯に理解する必要があります。
その理解に基づいて、商品やサービスを開発・提供することで、消費者は喜んで対価を支払います。
「消費者・顧客が何を欲しているのか? 自社の商品・サービスはその欲求にどのように応えるのか?」についての、具体的な活動が「マーケティング」です。

マーケティング活動の基本的なフレームワークや考え方を、日々の業務の中に取り込むと、仕事を進めていく中で、学ぶべきことがとても多く見つかります。
古くからの教えにも学ぶことがあり、近代において考え出された学問や理論なども参考になります。どんどん学び、吸収するべきでしょう。
社会人にとっては、マーケティングの基本の考え方は必須の学びだと思います。
皆さまも「マーケティング」に興味を持ってみてはいかがですか。
マーケティングにご興味をお持ちにの方は、マーケティングの基礎を学ぶ、「JMLAベーシックパスポート」をぜひご覧になってみてください。
必ずご自分のお仕事に活かされますよ。
「まずは、無料WEBセミナーに参加してみる」という方はこちら👇からご覧になってみてください。
堀内香枝
最新記事 by 堀内香枝 (全て見る)
- 地域力の相乗効果!ー5つの顧客経験価値を充足させる地域イベントー - 2023年10月3日
- 熱中症予防 夏休みを交替でとるこの時期、気をつけたい社員の体調管理 - 2023年8月4日
- データ分析+肌感覚の組合わせ~冷っとする危機に気づき 顧客の大量離反を回避し V字回復に成功~ - 2023年7月9日