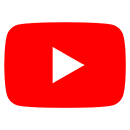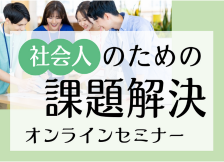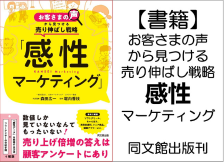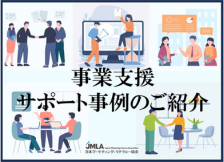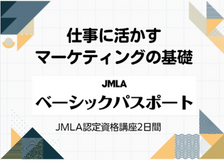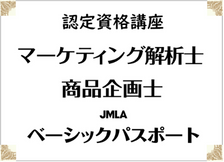JMLA 事務局 のすべての投稿
プロフェッショナル セールス
ベーシックパスポート

サービス産業におけるNeo P7導入の3ポイント
こちらの内容は、「商品企画システム化への道(7)~2つの研究会でP7活用の拡大」(WAKU LABO記事)から、サービス産業におけるNeo P7導入のポイントに関する内容を、抜粋・引用して掲載しております。
サービスとモノの違い
サービスという商品を考えてみますと、モノと異なり、次のような特徴があります。
分野が非常に多岐にわたり、しかも「日本式おもてなし」のようなフィーリング的な要素と、飲食店・ホテル・映画館・イベント施設・交通機関のようにハード的な要素や環境要素までもが商品への評価に複雑に影響します(サービス満点のレストランに入っても、周囲が騒がしかったり、トイレが古く汚いと印象は格段に落ちます)。
サービスという商品そのものは時系列的に進行し(例えばレストランでは予約⇒入店⇒メニュー決定⇒調理⇒食事⇒支払い⇒退店と時間を追って行われます)、しかも印象・感想・感動などが脳裡に残っても、モノのようにその後再度使われる訳ではなく、特に人的なサービスは保存できません。印象を悪くする要因はプロセスのどこにでもあり、ほんの一瞬の失敗が悪評価を招きます。大量に同一のものが生産され、反復使用されるモノと異なります。
サービス産業での商品企画にはこのような背景への考慮が必要です。
Neo P7を導入してシステマティックな(サービスの)商品企画を行う際は、次の3つのポイントに留意すると成功します。
Point1 イラストや写真
人的なサービスは無形のものが多く、文章のみではわかりにくいので、仮説の説明をなるべく具体的にします。補助としてイラスト、写真などを用いるのは効果的ですが、それがイメージを歪曲して伝えることも多いので、十分に注意します。
Point2 人的要素と装置的要素を分ける
人的要素と装置的要素は分離して扱わないと評価しにくいことが多いです。
<人的要素の例>
・店員の言葉遣い
・店員の態度や案内 等
<装置的要素の例>
・立地
・環境
・内装
・店内設備
・食器 等
ただし、最後のコンジョイント分析ではこれらの要素を一体化し、1つのサービスとみなして利用意向を尋ねます。
Point3 時間軸
時間軸で区分して考える必要があるかもしれません。前記の自動車、家電のいずれもが「購入前」「購入後」で分離してサービス案を提案し、成功しました。
これはサービス特有の考え方です。モノの場合には必要ありません。
☆新しいサービスをシステマティックに商品企画したい方は、こちらよりお気軽にお問合せください。
☆1月20日から始まる「基礎から学ぶ 商品機悪WEB講座5回コース」ものぞいてみてください↓
☆新商品・新事業の企画開発支援のWAKU LABOものぞいてみてください↓

『鬼滅の刃』と日本人の感性
コロナ禍において、映画「鬼滅の刃」が大ヒットしている。
映画業界にとってはとても素晴らしいことだが、ヒットの要因を考えると、すこしばかり今までの日常感覚と違う不条理の現実を感じる。
世界中がコロナの影響で生活が変化してしまっているが、日本人は独特の対処をしていると思う。
そこには良くも悪くも日本人の感性が表れていると感じる。
八百万の神を信じる農耕民族である日本人が培ってきた外界からの刺激に対する対処方法の一つであろう。
「鬼滅の刃」とは
そもそも、「鬼滅の刃」という物語は、大正時代を舞台に、人間である主人公が鬼と化した妹を救うために敵である鬼と戦うという物語である。いわゆる異世界の異能の持ち主たちの物語であり、現実の社会への対応に悩む少年少女たちが入り込みやすい世界なのだろう。
人は昔から変わらず漫画やアニメに対し、非日常の世界を求める。いわばひと時の現実からの逃避を求めるのであろう。特に少年少女にとっては、自分が生きるための何らかのヒントや力を得るためには重要なファクターになっていることは否めない。
大人までもが引き込まれる現実
現在コロナウィルスのために人々は非日常的な生活を送らざるを得ず、理不尽な世界に立ち向かっている。
その立ち向かい方が、日本人と欧米人とではかなり違っている。日本人は世界でも知られているように、従順で規則や慣習を守るということには律儀である。現在ほとんどの日本人はマスクをして生活をしている。しかし、欧米人はマスクというのは弱い人間がするもの(もちろん医療関係者は除くが)だなどという考え方を持つ人もおり、アメリカ大統領選においてはマスクをしないまま大規模な集会が行われ自分の意志や意見を表立って表現している。その結果感染の拡大を招く要因ともなっているのは問題だが。
つまり日本人は、「戦う」ことによるエネルギーを内側に向けてため込む志向性を持つといえるだろう。
そのため込まれたエネルギーはともするとフラストレーションとなり、その発散の場として「鬼滅の刃」という非現実の異世界の物語は、「理不尽な生活」から逃避し、ひと時の癒しを与えてくれているのだと感じる。あまりに厳しい現実への対処で目いっぱいになっていた心を潤してくれたのだ。
この現象を「いい大人が戦いのアニメ映画などを見て」という一言で切り捨ててしまってはいけない。
社会の変化や新しい芽に対し常に気を配ることは重要
この現象は良くも悪くも現実なのだ。おかげで映画関係者は大変潤っているのだ。
ビジネスの世界に身を置くものとしては、一つの「勝ちモデル」として、その要因を正確に分析し、そこに自社にとってのチャンスが見つけられないかという視点で捉えなくてはいけない。
世の中を何気なく見ていると自社にとっても大きなヒントとなることを見逃してしまいます。マーケッターとして、常に意識をもって世の中の動きを把握することが大切です。
皆さまも「マーケティング」に興味を持ってみてはいかがですか。
必ずご自分のお仕事に活かされますよ。